「ねえねえ、すごいんだってね!エクソシスト!」ある日、H美が私に言った。
「映画見に行こうよ!」
初めて「エクソシスト」を観たのは、忘れもしない川崎の映画館だった。
リンダ・ブレアの首は確かに回っていたし、緑色の汚物もなんだかものすごかった。
あの頃は確か、第何次かのホラーブームとやらでテンションはその次に訪れたそれよりもずいぶんと低めではあったものの、何かに付けて「エクソシスト」は摂り上げられていて、映画館で観る以前に「エクソシスト」の大よそのストーリーや見せ場なんて殆ど知ってたし、テレビでは毎日どこぞのお笑いタレントの首が回ってたし、何だかすごく「イロモノ」臭くて嫌だった。
2度目に観たのはビデオでだ。時間的にはどのくらい間があったんだろう。おそらく5、6年?私はすでに学生ではなかった。初めて買ったビデオがうれしくて、知ってる映画を片っ端から観ていたんだろうと思う。
![]()
映画は、まずイランの砂漠から始まる。
遺跡の発掘現場。まるでそれが仕組まれているかのように、メリン神父の手に握られた「パズズ」の首。ぐーっとカメラが砂漠を映していく。野犬の唸り声、ぶつかり合う牙の音、息遣い・・・・。土壁を、カメラがずうっとはいあがっていくとその遺跡の頂上の逆光の中、老神父メリンと、パズズが対峙している。
その時点ではまだ馴染みの無い、けれど、その時点からは深く記憶に残っていった邪神の名前・・・「パズズ」。
2度目というのは正確ではない。「イロモノ」としてなら何度か観ていた。9時台の映画劇場とか。その度首は回っていたし、汚物は緑色だったのに。この映画って、こんな始まりだったっけ?
白髪で、もう余生はのんびり好きな事に打ち込みたいんだいろいろあったしね、みたいな老人、メリン神父が、上品で質素で清潔そうな屋敷の中、霊感を受けるシーン。振り子時計が突然「ひたっ」っと止まる。老人の顔には、はっきりと苦痛が張り付いている。「またか・・・」。彼は決して私がやらねば誰がやる!とはりきって行ったわけじゃない。今度戦いがあれば、きっとそれが私の人生最後の戦いになるだろうという予感、死の予感。「神の名において」戦い続けてきたであろう老兵の最後の決意。
「お前は行って、すべき事をするがいい」と運命を受け入れた彼のお方も、きっとこんな悲痛な面持ちをしていたに違いない。
![]()
ワシントン、ジョージタウン。映画の撮影現場。
彼女はいつもぴりぴりしている。彼女特有の甲冑を身に纏うかのように。颯爽と。大女優「クリス・マクニール」。
彼女を見つめる野次馬たちの中に彼の姿もある。若い神父「デミアン・カラス」。
彼らはまだ、これから彼らの身に起こる事を、何も知らない。
「エクソシスト」という映画に出会ってから、私は何度このシーンを繰り返して観ているだろうか。この時この瞬間、彼らは確かに出会っていたのだという事が、これほど重い意味を持つ映画が他にあっただろうか。ここで彼らが出会っていると同時に、メリン神父は「啓示」「霊感」を受けているのだ。
「正義の味方」という言葉があるが、彼らは一人も「正義の味方」じゃなかった。ある宗教者の「サタンはそそのかすのでもなければ誘惑するわけでもない。始めは自由を平和をとやさしく語りかけるのだ」という言葉が思い出される。
神父「メリン」神父「カラス」。これから彼らはこの絡んだ運命の糸に縊り殺されていく。一人の少女を救うために。・・・己の罪を懺悔しながら。
迎えに来た車を断って、歩き始める女優。
町角ですれ違ったシスターたちの僧衣が、風に煽られて美しい流線形を描いている。
そしてオープニング。
今はもうだれもが1度は聞いた事のある「チュウブラベルズ」。
「始まり」そして「予感」、「不安」。
![]()
少女の家は裕福である。
映画の解説をしている方々がどの程度の暮らしをなさっていらっしゃるかは知らないが「何の変哲もない中流の家庭」というのはポニーは飼えない。
彼女のための若い白人女性の世話係「シャロン」、その他にハウスキーパー夫婦、使用人は3人。彼女のためには個室のほかに小さいがプレイルームも有り、彼女の造った亀だのなんだのの粘土細工が並べてある。そこは彼女の秘密の部屋にもなっていて「キャプテン・ハウディー」と話すための「ウイジャ板」もあった。
彼女の名は「リーガン・マクニール」。
前述の「クリス・マクニール」の一人娘である。
母親は社会派の真面目な有名女優であるが、今はもう1時期の栄光はなく、彼女にとってもその「名女優」という言葉は重くなり始めている。今彼女を支えているのは「リーガン」と「かつて名女優だった」というプライドと、気は弱いが気立てのいいバーク監督だけである。
このドラマには父親は出てこない。リーガンの誕生日にさえ何もしない!と母親が電話に向かってがなりたてているシーンで1度だけ、離婚したか別居しているであろう父親の影を思わせるシーンがあるだけだ。
そう言えば、リーガンの教育係兼雇われ友達?権母親の付き人としてこの家に同居している「シャロン」の存在もとても印象深かった。
この「リーガンの父親」と「シャロン」は、この作品の中では徹底して無視されていく。「リーガンの母親」は、とりあえず「最愛の我が子」と「己に突然降りかかった災難」と「その災難で苦しんでいる家族に何の助けもよこさない無責任な父親」意外に冷徹といっていいほど全く興味を持っていないのだ。「付き人」は、その状況にあっても「リーガンの母親」の「ファン」であり続けるのに全く無視され、思われている当のご本人は「リーガンの父親」にはっきりと拒絶されていくのだ。
![]()
そしてもう一人、物語の重要な登場人物。彼の名は「デミアン・カラス」。
神父であるが、人々の相談役やらカウンセラーやら何やら、とにかくその日常は忙しい。信頼のおける好人物である。
だが、そんな彼もたった一つだけ大きな悩みを抱えていた。「母親」である。
自分は神父として人々に奉仕し信頼も厚いが、彼の母親は体の自由が効かないほど高齢で病身、母思いの彼は何度も説得を試みてはいるものの彼女は病院へ入るのを断固として拒否し続け、一人都会の片隅で暮らし続けている。彼女の心の友は、1日中鳴らし続けているラジオの宗教放送だけである。
彼は休みの度その母親に会いには行くものの、そこにあるのは母親の果てしない「ぼやき」と「恨み言」だけである。「信頼の厚い好人物」であるはずの彼は「病身で苦しんでいるか弱い母親の面倒さえ見ない無責任な息子」でもあるのだ。
彼女が彼を「デミー」と幼名で呼ぶ声が、映画の最後まで耳にこびりついて離れない。私は、母親から呼び捨てにされても構わないが「ちゃん」だけはつけて呼ばれたくないと思うもの。
ここで一つ心に留めておいて頂きたいのは、彼は決して「2面性」のあるずる賢い人物ではないという事だ。心からみんなの幸せを思って日夜努力している。努力しても努力しても、次から次へと人々たちは己で努力する事無く「どうにかしてくれ」と取るに足らない悩み事を持ち込んで来る。
母親の事は、夢にうなされる事さえある。他の依存心ばかりの他人のように「どうにかしてくれ」と取りすがって来る。にっこり笑って「ご機嫌いかが?」と挨拶するのでさえ苦痛なほど彼の精神は追いつめられ、今しも溢れんとする「表面張力状態」なのだ。
![]()
この一言から恐怖が始まった。何を言ってんだか、この子は。私は疲れてんのよと、億劫そうにベットの端を我が子に開けてやる母親。そう言えば、天井でねずみが騒ぐからって言ったのに、あのぼんくらたち、何も無かったって言ってたわね。最近、奇妙な事ばかりで家でさえくつろげない。
この子ったら、ほんとにどうしちゃったのかしら。私が付いててやれない分、多少はわがままに育っている事は認めるわ。でも今日のこの子は確かにおかしい。パーティーなんていつもの事なのに、こんなに大きいのに、みんなの前でお粗相するなんて。ああ、どうにかしなきゃ。みんなに後でなんて言われるか。
始まりはいつも静かにやって来る。
ご多聞に漏れずこの母親も、我が子の異変に気づいているのにうまくパズルが嵌まらない。「どうして早くに手を打たなかったの?」と、口さがない他人たちは平気で責めるが、本当にこういう形で不幸は突然やって来る。
純真で無垢だったはずの我が子がいやらしい暴言を吐きながら乱れ狂う姿は、かの母親にとってはショッキングという域を遥かに越えていたはずである。これを観ていた当時は母親ではなかったが、今こうして思い返してみると、あの瞬間あの母親は何が一番恐ろしかったんだろうかと思う。
娘の吐く暴言に怒っていたわけではない、何か恐ろしい力が働いているかもしれないと思ったのもかなり時間が経った後である。無論、これを他人が見たらどう思うかなどとは考える余裕すらなかった。何より彼女が恐怖したのは、我が子の身体が傷つけられていく事ではなかったのだろうか。
うちの子があんなになったらどうしよう・・と思う私同様、その母親も、緑色の汚物を吐きながら正体を無くして暴れまわる我が子の姿に、ただただ動揺し、おろおろと病院を訪ね歩くしかなす術はなかった。
![]()
ふざけんじゃねえ!である。
最新の医療機器は、我が子の体をただいたずらに痛めつける。娘に針が刺し込まれるたび、自分の身が切られる思いがする。なのに挙げ句の台詞がこれである。
この母親は神を信じていなかった。娘に「悪魔」とやらが取り憑いてしまうまでは。
それを云々する気はないが、特にこの映画が創られた1973年は少なくとも人類の何分の一かが「無神論者」になっていた時代である。その点でもこの「エクソシスト」という作品の重さを感じずにはいられない。
悪魔が囁く台詞である。その全てが、カラス神父の心の傷を深く抉っていく。僕は、神経科の医者だから!神父だから!と冷静さを、己を見失わないよう格闘している姿が、痛ましい。
彼には支えになる恋人もいない。すでに母親もこの世にはいない。唯ひとり親友である「ダイアー神父」だけが彼の心の支えにはなっているものの、彼の心の奥深くの痛みまで理解していたとは思えない。
彼が戦いに疲れ果て部屋の外へ出ると、リーガンの母親がやはり疲れ果てた顔をして彼に聞くのだ。
重く巨大な十字架は彼の肩に深く食込んで、もう、ここで止める事も引き返す事も出来はしない。
この後、ご存知の「悪魔との死闘」が繰り広げられるわけだが、この部分はあえて割愛させて頂く。私は今まだこの映画のこの部分だけがこの映画をヒットさせたソースである事に納得がいかない。これはあくまでもオプションであって映画の本筋ではないと思えて仕方が無い。
![]()
何もかもが終わったかに思える静寂の中、床にはメリン神父の亡骸。
リーガンはまだ「取り憑かれたままの姿」でベッドの支柱に放心したようにもたれかかっている。
必死で蘇生を試みるカラス神父。振り向くとリーガンが肩をゆすりながら低く笑っている。
私はこの時初めて、本当の悪魔の姿はこれだと思った。
勝ち誇っているわけでもない、喜んでいるわけでもない、自分に逆らったものに当然の報いを与えてやったのだという、満足げな不敵な、そしていかにもふてぶてしい笑い。
バーク監督も、こいつがやったらしい、この少女をいたぶり続けているのも、私たちを苦しめ続けているのも、この「悪魔」がやっているらしい・・・けれど、確信はやはり無かったのだ。その笑いを見るまでは。
少女を渾身の力を込めて殴り付けながらカラス神父が叫ぶ。彼に、その後どうしようなどという策略はなかった。ただそこには「怒り」と「恐怖」だけがあったに違いない。
少女の肉体を持った「悪魔」。伝説でしかないと思っていた呪われた魂。
その凶凶しいものが、現実に自分の目の前にいて、メリン神父をその手にかけ、自分と自分の母親を愚弄し、少女を辱め、何人もの命をまるで玩具のように奪い去った。
カラス神父の理性の箍が吹き飛んだ瞬間である。
そうして、カラス神父は、物語の最初からまるで人生そのものの暗示のように登場する長い長い階段を転がり落ちていく。「悪魔」をその身に抱えたまま。
親友のダイアー神父が握る手が、弱々しくそれに応える。
彼は、母親の死を看取れなかった事を悔いていたのだろうか。自分が確信できなかったために、メリン神父を助け得なかった事を悔いていたのだろうか。人々を救おうと就いた聖職であったはずなのに、自分の非力さを・・・悔いていてのだろうか。
![]()
誰もが「正義の味方」じゃなかった。
誰もが、懺悔をしたかった。
誰もが確信していなかった。
「悪魔」は、彼らの心にあった「罪の意識」をほんの少しだけ刺激したに過ぎなかった。
ここに描かれている「悪魔」が実在したとするならば「神」は?
この映画は、それでも「神」の存在を認めてはいない。
![]() END
END

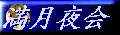
|