映画は、おばちゃんが線路を跨ぐ陸橋から降りてくるシーンから始まる。
そこらにあるような町の風景、朝のラッシュ時には開かなくなる小さな踏切のある2車線の道路から、少し入った路地の途中にその家はあった。
車さえ入れない路地の、向かいの家とはトタン塀囲いでかろうじて仕切られているような庭付きの二階建ての一戸建て。庭にはゴルフのパット練習用の小山が作ってあるかもしれない。40代くらいの夫婦と高校生くらいの兄弟が暮らしていそうな。
だがその家にはヒト気が無い。玄関ドア、二階のベランダの張り出しのペンキは剥げかかり、延び過ぎた雑草と、庭木もところどころに立ち枯れが始まっている。
おばちゃんは、その家の門の前でふと足を止めると、ブルッと身震いをして眉をひそめ、通り過ぎて行く。
庭の奥から猫の声がする。
「にゃあぁぁぁぉぉぉぉぉぅ・・・・・」
![]()
物語は全て断片で、まるでパズルのピースのように私たちの前に次々と並べられていく。
男の名前は小林(柳ユーレイ)、小学校の教師である。妻は臨月近い妊婦で夫婦仲は上々、暮らしは質素で穏やかだった。
彼は今、ずっと登校していない生徒が暮らすその家の前にいた。伽椰子という生徒の母親の名前には憶えがあった。大学時代暗いと皆から敬遠されていた女。
卒業後担任する生徒の母親となったその女とは一度だけ面識があったが、顔ははっきりとは思い出せなかった。
生徒の名前は俊雄。イラストレーターの父を持つ画才のある子供。
玄関ベルを押しても返事はないが、門にも玄関ドアにも鍵がかかってはいない事は妙だった。左手から裏口に廻ろうかと踏み込んでみると、足元のベニヤにハエがたかっている。つまみあげてみると大量の血と髪の毛があった。やはり何かおかしい。
ふと気がつくと浴室らしき窓から子供の手がにゅうっと突き出ている。
「俊雄君?」
死んだような目の子供。顔には大きな青痣ができている。
「せんせぇぇ・・・」
「俊雄君だね、お母さんは?・・・いるの?」
子供の手がすぅっ奥に消え、何かが落ちる大きな音がした。
彼は玄関から大急ぎで家の中へ駆け込むと、一階の子供がいた風呂場へと。
彼が入ったとたん鍵が閉まるでもない、怪異が起こるわけでもない、彼は純粋に教え子を案じている一教師であり、生徒は、某かの虐待を受けていたか、長く放置され続けた憐れな子供であった。・・・・・だが、彼がこの家に獲り込まれた瞬間なのである。
この断片の終わりは、小林が道沿いの小窓にもたれ愛する妻に遅れる旨携帯で連絡を入れているシーンである。
小林の顔がゆっくりとロングになっていき、窓。長く尾を引く猫の鳴き声。小林がいる窓の奥には傷ついた子供の顔。猫の声は、子供の喉から発せられていた。そのままカメラはお構い無しに退いていき、二階のベランダと窓が映る。
そこには・・・・。
![]()
次の断片は初夏。二階の件の窓のある部屋に女子高生と家庭教師がいる。
高校生は柑菜、健康的なイマドキの娘である。家庭教師は由紀、大学生で柑菜の親戚かもしれない。
「ねぇ、本当にここまでやったら彼氏の事教えてくれる?」
「わかった、じゃあ、ここまでね」
上の空で返事をする由紀。彼女は今、微かに聞こえる物音が気になって仕方がない。彼女の大嫌いな猫が、何かを引っ掻くような。
「ねぇ、ほんと、聞こえない?ね?・・・変な音」
「ん、もう、そうやってごまかすからぁ」
由紀はこの後音の正体を知ると同時に、その家の暗黒へと引きづり込まれるのだ。
学校の断片では、柑菜の弟の彼女が犠牲になる。
死体置き場の断片。
奇妙な形に盛り上がった死体の前で、刑事がつぶやく。
「こりゃー、心臓発作でしたなんて言い訳は・・・通用しねぇよなぁ」
解剖医が苦渋に満ちた表情で応える。
「こんな死体見た事ないですよ。混ざっていたのは別の人間の下顎です」
次の断片は、その母親がパートから帰ってきた時だ。
家にいるはずの二人の子供の姿がない。家庭教師の由紀の姿もない。中学生の息子の彼女からの電話の途中で、誰かが帰ってきた気配があった。ちょっと待っててといいつつ二階の子供部屋へと続く階段を見ると、そこには夥しい血が。
見るとセーラー服姿の娘がずるりずるりと二階へ上がっていく途中だった。だが、柑菜だと思ったそれは血みどろで、服はずたずたに裂け、足も背骨も妙な具合にひしゃげている。
倒れていたなら、おそらく彼女の母性本能はまっすぐに娘の心配をして狂ったように救いを求めたに違いなかった。が、しかし、ソレは惨憺たる様子のまま立って歩き、階段をじりじりと上っていく。
ソレは、母親の見ている中階段を上りきった所で天を仰ぎ、ひしゃげた身体を伸ばし、止まった。彼女は手で口を押さえたままうっかり叫びだしそうになるのを堪えて、聞いた。
「柑菜?!・・・・・誰なの?!」
奇妙にひしゃげたその物体はゆっくりと母親の方に振り向いた。
断片は、小林が電話をかけているシーンに戻る。
最次の断片はその家を管理する不動産屋の断片である。
![]()
恐怖はちりばめられているのではない、そこに「落ちて」いるのだ。
絵的にはおそらく片付けられているはずの居間が乱雑に散らかっている。投げ出された薬箱、痣だらけの子供の膝にぞんざいに当てられた血の滲んだままのガーゼ、綺麗に整理された風呂場で見た血塗れの惨劇の幻覚、猫。
その部屋の外はまだ昼間なのだ。一階の奥にある、キッチンのガラスには陽光がさしているのだ。逃げ出すのは今しかないのに、その暗い部屋に男は引き止められていく。
子供の親が帰ったら。
そのドアを開けたら。
この家を出たら。
脱出口はいつでも、恐怖の暗黒のすぐ脇にあるのに。
押入れの奥から聞こえる微かな音、麦茶、多すぎる猫の置物、はげかけたベランダのペンキ、壊れていくCDプレーヤーや44444444とメッセージする携帯、横柄な中年の女教師の消失、職員室、裸足の子供の駆け回る足音、そして、猫。
彼氏を置いて帰ればいいのに。
先生の言う事なんか守らなくていいのに。
明日になったら、なんとでも言い訳すればいいのに。
学校という物言わぬ暗黒の要塞。
好きな子に執着し、ノートにびっしりとしたためられた執念。胎児、ビニール袋、一升瓶の清酒・・・・・。
そこらで見かける恐怖映画のように、怪異は見えざる力によって強制的に閉じ込められた犠牲者に起こるのではない、ドアも窓もいつでも開いているのだ。
そして清酒は、霊的な力を呼吸し、飲む者によって味が変わる。
その一粒一粒の粒子が、見ている者の目の前でゆっくりと形を成し意味を持ち、気がつくとすぐ脇にいて、「ねぇ」といきなり語りかけてくる。
外はまだ昼間なのに、その部屋だけが妙に暗いなと思う瞬間、押入れの奥から聞こえる微かな物音が、いても立ってもいられないほど気になったり、すぐ隣の部屋にいるはずの兄弟が妙に静かになってたり。声をかけようかどうしようか、下に降りてテレビでも付けて、そういえばポテチの買い置きがあったはずなんて、その時気がつきさえしなければ、見過ごしてしまうような恐怖。
3時から夕日が落ちる6時頃まで、逢魔ヶ刻、とそういう言い方をした気がする。
外はまだ、陽光の名残が十分残って明るいのに、家の中に巣食う夕闇が、どきりどきりと息づいている。
おそらく、「読者の恐怖体験」か何かで読んだエピソードかもしれない、どこかで見かけた私自身の原風景なのかもしれない、そういう家は確かにいつか近所にあって、そこにはヒトが住んでいたのだ。それは私の同級生だったのかもしれない、・・・いや。
いつか見た悪夢だったのかもしれない。
ともかく夜中に一人で、部屋を暗くしてみる事だけはオススメしないでおこう。
もう見たいくない〜!とビデオのスイッチに手をかけたまま、でも結末を見ないままでは終われない、某かの決着があるはずなんだ、だってこれはフィクションなんだから。作り物なんだから。そう考えているうちに断片は次々と目の前にほおり投げられ積まれていく。
![]()
昔々、横浜と渋谷を繋ぐ東横線沿線に多摩川園という弱小の遊園地があってスリラーカーというアトラクションがあったのだが、何十年ぶりかであの恐怖を思い出した。
お化け屋敷というのは、徒歩が基本で怖けりゃ立ち止まれもするのだが、カーというだけあって観客を乗せたそれは決まった通路を決まった速度で走りぬける代物なのだ。しかもここぞというところでがくんと止まったりもする。今でいう体感型の原型ともいえるだろう(笑)
だが、止まるときに出てくるのはちゃちな衣装の小妖怪ではない、スペシャルエフェクトでグロテスクに彩られた焼死体が天井からいきなり降ってきたり、人海戦術で無数に突き出された生腕が、洋服に微かに触れたりする瞬間なのだ。
もうやめて!ここで降ろして!でも降ろさないでー!と、泣き出す事は言うまでもない、が、そこで降りたらおそらく一生この暗闇からは出られなくなる。途中下車は不可能なのだ。車は大泣きしている私を嬉々として次の地獄に送り込む。
そして最後の最後の瞬間、暗闇が数秒続いた時、顔を何かがべろりと舐め、母の待つ平和な陽光の中へと車は脱出するのだ。振り向くとそこには黒い暗幕が垂れ下がっていて、それが仕掛けだったと笑って終わる、それがスリラーカーである。
この映画に終わりはない。
暗幕の垂れ下がった終点のちゃちな仕掛けは見えてこない。
暗闇が数秒続いて明るい陽光の中に出たとき、ああ、よかったこれは作り物じゃないのと、胸なでおろした瞬間、そこには、あの映画にあった押入れが厳然とあって、微かに何かが引っ掻くような物音が。
![]()
今、私が一番着目している黒沢清らが推している若手の監督だそうである。
日本の恐怖映画界は変わるかもしれないと、絶賛する言葉はひとまずここらで括っておくとしようか。
![]() END
END

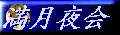
|