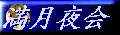Happy Birthday 
ドライブに行こうと言い出したのは、美奈子だった。
今日は俺の誕生日。
ポケベルはまだ沈黙していた。
澄んだ空には満月。湾岸線の道路もこの時間になると行き交う車も少なく快適だった。
「ねぇ、憶えてる? 初めての二人だけの誕生日。私、今でもあのホテルに行くと思い出すわ。あなたからのプレゼントは、ルビーをあしらったプラチナのペンダントだった」

美奈子は陰気な女だった。笑い声は結局三年間ほとんど聞いた記憶が無い。彼女の作る食事はいつも手の込んだロシア風の煮込み料理がメインだった。味は悪くはなかったが、それを俺の事を考えながら日がな一日煮込んでいる姿には、執念のようなものをさえ感じる事があった。
「父の病院ねぇ、やっぱりもう駄目だって。もともとさほど大きい病院じゃなかったし、こうなる時が早いか遅いかだけだったのかもしれない」
その恩着せがましさ。こいつにとっては俺も「さんざん世話してやった」一人に過ぎないのだ。世話して手を施して丹精したコレクション。 「あなたのような優秀な外科医がいてくれて、一時は盛り返した事もあったけど、父ももう長くないし、あの病院の建物も手放して、もっと質素に二人でやって行きましょうね」
解散が決まって義父について行くと言い出す者は一人もなかった。ワンマンな医院長と言いなりな母親と金銭感覚の欠落した娘と。総合病院とは名ばかりの、5階建ての鉄筋の建物の中には、年寄りと妊婦がほとんどだ。万年人手不足に悲鳴を上げている看護婦たちの矢面に立たされるのはいつも入り婿の俺だった。

「あのな、美奈子」 「なぁに?」 「いや、・・・お義父さんの容体が落ち着いたらでいい」 「大丈夫よ。いつかはそうなるって覚悟は出来ていたし」
いつかはそうなるって、病院か父親か。おまえはいつも大切な事が何一つ見えてない。
「そうそう、あなたにプレゼントがあるの」 嬉しいと言う一言が口の中で凍りつく。言え。今言わないときっとあとから後悔するに違いない。
「そいつは嬉しいな」
おまえになんかわかるもんか。今まで三年間、おまえにわかった事など一度もない。見た目は上品に振る舞っていても、牛のように愚鈍で寝ぼけた神経にはわかるはずなんかない。 恵美にやったイヤリングだった。うちの内科の看護婦だった女だ。こいつと違って活発で今回の決断もあいつの一押しが無かったらきっと出来なかったように思う。いっしょにまずは田舎に行って、小さな病院に勤めながら一からやり直せばいいじゃないと言われた時には、真っ暗な人生の中に一筋の光明が射したような気がした。一ヶ月前、病院を退職し、早々に二人で住むアパートを決めてきたのも彼女だった。 美奈子にはもう俺の将来をどうこうできる力はない。これからは恵美が俺を導いてくれる。こうして俺を手に入れたように、未来も恵美が切り拓いてくれるに違いない。 恵美と過ごす時間が、こうして毎日陰気な息の詰まるような会話を続けていなければならなかった俺にとって、どれだけ救いになっているか。ポケベルが手術中でもおかまいなしに鳴るのには辟易したが、俺が病院にいる間はEMIと名前が入ったメッセージが届くのは新鮮だった。 昨日今日と休んだおかげでメッセージが無いのは寂しかったが、今夜、俺の誕生祝いの支度を終えたら、ポケベルを鳴らす打ち合わせになっている。恵美にはこのポケベルを鳴らすまでにはちゃんと別れ話はしといてよね、と、別れ際に念も押された。 あの抵当に入った屋敷の食卓で、二人きりで息苦しい会話を繋ぎながら、例年通りのこってりと手の込んだ夕食をといったコースの誕生日になると思っていたのに。こうして車の中にいて、美奈子は助手席にいる。まさかEMIとなんかよこすんじゃないだろうなと思うと気が気じゃなかった。

「そんなに、ポケベルが気になる?」 「え。」 「あなたさっきから何度も内ポケットを気にしてるから」 「そ・・・そうかな? 救急で患者が入ったらと思うと落ち着かなくて。今日は満月だろ? 満月の日は事故が多いって言うし」 美奈子が不意に笑い出した。
「可笑しい。・・・満月の日は事故が多いですって? そんな事あなたが考えてるなんて」 初めて聞いた彼女の激しい笑い声はかん高く、真っ暗な車内に響き渡った。
「止めろよっ!!そんなに可笑しいかっ!」 気が狂いそうだ。 「ねぇ、車を止めて」
俺はハンドルを乱暴にきると、ちょうど通りかかった橋の膨らんだ部分の路肩に車を止めた。 「・・・いい加減にしろよ。勘弁してくれよ」 もうずっと堪えてきた事が、思わず口をついて溢れ出した。
「こんな時に言い出したくはなかったけど、俺はこの病院を出て行こうと思う」 美奈子は俺の目を見たまま、悪戯っぽくくすりと笑った。
「あなたにお誕生日のプレゼントをあげる」 美奈子が後部座席から取り出したのは、細長い長方形の派手なリボンのついた箱だった。それをぐいと俺の目の前に突きつけながらこう言った。 「開けてみて」 俺は言われるままにその箱のリボンを解き始めた。箱はかすかに水分を含んだように重く、しっとりと冷たかった。派手な包装紙を乱暴に破くと、純白の光沢のある厚紙で出来た箱だった。蓋に手をかけ、それを開ける瞬間、美奈子がぼそりと呟いた。 「あなたの今、一番好きなもの。どう? 当たってたでしょう?」 純白のチュールレースに埋もれたそれは、電話機を握るのにちょうどいい鉤型に凍ったままの左腕だった。切断面は凧糸できっちりと巻かれ、どす黒く変色した薬指には、俺が恵美にプレゼントした婚約指輪が光っていた。
空には満月。 この道は美奈子と二人で何度も通った道だった。俺の声は喉の奥で凍りつき、ただの吐き気へと変化し、俺を呼び出すはずのポケベルは沈黙したままだった。
END 
|