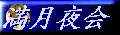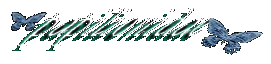
「ボクは、先生の玩具だったのかもしれない」
青年は、かちりと音をたててティースプーンを皿に置いた。 「でも」 赤々と燃える炎を見つめたまま青年は話を続けた。 「本当に愛してくださっていたのかも知れません。・・・・・・今はもう、どうしたって確かめる事などできないけれど」 青年はそう言うと、口の端だけで弱々しく笑った。
鬱蒼とした森の一角にその屋敷は建っていた。 「旦那、ほんとにあの屋敷に行くんですかい? あすこに客だなんて、おいらこのへんで長い事商売さしてもらってるが初めてでさあ。あすこの大旦那は、どこぞの偉い学者さんだったってぇ話しだが、噂じゃ気が触れ……おっとと、いけねぇな。喋りすぎだ。聞かなかった事にしてくだせぇよ」
この森の馬車の入れる所までと、頼んだ御者が飲み込んだ言葉が何だったのか、屋敷を実際に目にした時、初めて理解できたような気がした。 行き届いたというよりむしろ神経質なほどに整然と造られた庭園と、その奥まった中央に幽としてそびえるこの屋敷は、その鬱蒼とした木々の造る影と、中天にさしかかった太陽の光とで何かで見た宗教画、いや、もっと言うならばまるで巨大な墓標のようだというのが正直な私の感想だった。
『拝啓
長い事何の連絡もしなかった私を、君は覚えていてくれただろうか。
君に話した事があっただろうか。私がなぜ、あれほど彼らに固執しているのかを。
だが人間とは不思議なもので、あれほど激しく嫌悪していたものが、ある日突然魔性の如くの魅力をもって私の心に住み着いたのだ。後にそれまでの嫌悪感は、一種の自己防衛本能だったのではないかと思えるほど私は、彼らに浅ましく跪く恥知らずになった。 君に、無性に会いたい。
おまえはこのまま地獄に堕ちるのではないと言ってくれる人間と会いたい。
君と、会えなかった時の為に。 ハワード・F・バーノン 日付』
私が、今ここにいるきっかけとなった手紙が届いたのは、二ヵ月ほど前、季節は夏から秋に移り変わろうとしていた頃である。
|