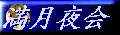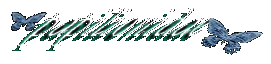
この手紙の差出人、青年の言う先生とはつまり、私のいる大学に十年ほど前、鱗翅目の講師としてやってきた男である。 私も本業の傍ら、蝶の収集には道楽程度の興味があったし、歳が近かった事も手伝ってか、彼とはすぐに親しく付き合うようになった。 その頃すでに彼の生活は、蝶で埋め尽くされていたと言ってもいいだろう。彼の蝶類のコレクションは、学術的と言うよりむしろ狂気に近いものがあった。この仕事に就いた事自体がそもそもの間違いだった、僕は彼らに溺れているのだと、酒を飲むたび自嘲するかのように語っていた事を思い出す。 めずらしい種類がいたと聞けば何ヵ月も出たきり帰らない。大学にはほとんど顔を見せず、人との付き合いも私を除いて全く無かったと言っていい。それを世間が許すはずもなく、二年ほど経った時、ふいと突然姿を消したきり二度と大学に戻っては来なかった。
私との付き合いも、それを境にふっつりと途絶えたきりになっていた。
彼からのあの手紙も、もちろんきっかけにはなった。だが、本当の理由は、それだけではなかった。私は彼に、えも言われぬ魅力を感じていたのだ。
きっと私は、私が一生かかっても踏み切る勇気の無かった仮の人生を過ごしている己れの姿を、彼に見いだしていたのだろうと思う。 しかし、この屋敷で私を待っていたのは、彼が私の到着を待たずして他界したという報せと、唯一彼の残した財産であろうおびただしい数の蝶の標本と、この青年であった。 「僕は、先生の助手として五年間、先生と共に暮してきました。思えば長いような、短いような五年間でした」
青年の声は澄んだアルトで、穏やかに話しているはずなのによく通った。
「君は、」
「君は、彼が亡くなった後、ずっと一人でここに住んでいるのかね」
「私は度胸の無い人間だから、こんなに深い暗い森の中でなど、独りじゃとても居られない。ましてやこんな風が吹く夜など、恐ろしいとは思わないのかね」
………それに、世の中には、ここよりずっと恐ろしい場所がありますから」
私達のいる広間は、いや、この広間だけではなく、この屋敷のほとんどが、蝶の標本で埋め尽くされているのだろう。
その一つ一つが、まるで今にもはばたき始めるかのような完璧な姿。それぞれに記された彼らしい詳細なデータ。
彼と親交のあった時期のコレクションとは、比べものにならないほどの数だった。
|