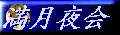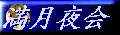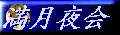夏の夜の恐い話"しょにょ1"
「かゆみ」
血のにおいの恐い話。(98/07/12-13:38)
私は連日の熱帯夜の中で汗をにじませながら切なげに布団で何度も寝返りを打っていた。
もう夜中の3時すぎだ。今夜も眠れない。
電気を消した部屋の天井を見上げていると、何か暗い闇に吸い込まれるような錯覚が起こり、目をつぶっていると自分の感覚神経が何か一つの丸い固まりとなり、その固まりが圧力のある闇の圧迫に翻弄され、見えない力にいたぶられ、空気の抜けたゴムボールのようにもてあそばれ、変形を繰り返すたびに軽いめまいを誘発し、苦しさと暑さにもだえ苦しんだすえ、両目の奥にある感覚神経をしびれさせ、平衡感覚を失い、これ以上目をつぶっていると途方もない闇の奥底に吸い込まれそうになり、はっと目を開ける。
そんな事を2,3度繰り返していたら、全身に汗が吹き出し、布団がじっとりと湿気を帯び、何か体中が痒くなってきた。
無意識に全身をかき始めたが、特に右手のひじのカユミは異常だった。
目を閉じて、淡々と腕をかきつづけていると、かいていた指先にヌルッとした汗と違う感触が伝わった。しかし、カユミは逆立った神経を挑発するように増していった。
おぼろげになった意識の片隅で、自分の腕をかいている音だけが闇の中で聞こえる。
しばらくするとカユミはおさまったが左手の指に残ったヌル付きが気になり、指をこすりあわせると、かなりのヌル付きがついているようだ。目を閉じたままその左手の指を鼻に近づけ、ナメてみた。
血だった。
一瞬私の中の古い記憶がよみがえった。
あれは21か22のときだった。
私は横浜にある市大病院に仕事で2,3年、電気工事で従事していた。仕事も順調に進み、立場も班長クラスになっていた。
中で一番難しい、地下の変電室の高圧トランスを取り替える仕事を明日に予定されたその日、私はICU(集中治療室)と緊急手術室の電気の切り替え工事を受け持つ事となった。
当日仕事も順調に進み緊急手術室に取り掛かろうとした時、長い廊下の端のほうから大きなざわめきと共に急患が運ばれてきた。
やむをえず、私は、しばらく待機する事になった。
40分もまっただろうか、手術も終わり、患者がICUに移され、出入り可能になった手術室に私は踏み込み、仕事を展開した。
はじめは気にならなかったが、空気が湿り気を帯び、人肌のぬくもりを持ったそれは私一人を包み込み始めていた。
それは、かすかに漂うほのかな甘いニオイだった。
その甘いニオイが私を取り巻き幾重にも重なり息苦しささえも感じるようになってきた。
血のニオイだった。
大量の血のニオイは甘味な芳香を漂わせ私の逆立った神経の隙間を埋めるように感覚の中に溶け込み、そして、私の中に眠っていた何かが、目を覚ました。
動物のもつ特有の闘争、殺戮、生存本能とも呼べる、何か今までに味わった事のない何かがフツフツと沸騰し始め青白く、冷たい感覚が胸を埋めた。
私はこの時、血が血を呼ぶ、と言う感覚を始めて体感した。
理性とか、とは違う禁断の領域の何かが自分の中に鼓動し始めた。
私はたまらず、手術室を飛び出し、廊下の端にある長椅子に崩れ折れるようにへたり込んでしまった。
遠い昔先祖たちは、争いに付き物の血を、本能の導くままに受け入れたのだろう。
治安の行き届いた現在、多数の人間たちの中に化石のように硬化し、封印されてきた、この本能は、ある時突然、猛暑によって、あるいは人間関係の摩擦によって、点火し、それを制御する事は、非常に困難だろう。それは、あなたの、そして私のもつ本能なのだから、、、、
いつしか、その本能が何かのきっかけで目覚めたら、あなたは、それをくいとめることができますか?

夏の夜の恐い話"しょにょ2"
「健康管理」
薬の恐い話。(98/07/14-01:47)
私も40歳に近づき、最近は健康にもずいぶん気を使っている毎日だが、先日ちょっとした気の緩みから夏風邪をこじらせ通院を余儀なくされ、一週間に一度薬をもらっているが、これが一向に具合がよくならない。
薬の種類はと言うと、咳止め3種類に抗生物質、そして胃薬だ。
自分の不規則な生活を棚に上げ、ほかのせいにするのも、おこがましいもんだが、いかんせん、治りがよくないのだ。
以前何かの本で読んだ事があったが、どうもこの、抗生物質が気にかかる。
抗生物質とは、誰もがご存知の薬で、フレミングが青カビから発見したのが始まりらしく、これがまた殺菌作用に優れた能力を発揮するらしい。
ストレプトマイシン、クロラムフェニコール、テトラサイクリンそして数ある中で、最も強力な殺菌力を誇るメチシリン、、、、、
性病を始め、あらゆる病気のもとである病原菌を退治してくれる特効薬。これらは人類にとって大いなる福音をもたらし、繁栄を約束してくれた。
だが、、、近年、これらの抗生物質に耐性を持った病原菌が人類に牙をむき、反撃を始めたのだ。ゆえになぜ?
原始的な構造の細菌でも、種族保存の機能が働き薬剤耐性を持ったのだ。
文献にも記載されていたが、なんと耐性病原菌を作り出したのも人類だったのだ。
さまざまな病床に伏した人たちが集まる病院内での医院内感染を防ぐため、抗生物質が多用され、それがもとで、病原菌は言うに及ばず、普段私たちを取り巻いて存在している常在菌(どこにでも存在する無害な菌)にまで悪魔的な力を持たせるに至ってしまった。
この常在菌が薬剤耐性を持つとどうなるのか。
黄色ぶどう球菌は、常在菌の一種なのだそうだが、耐性を持ってない彼らは、たまに食中毒の原因になったりするのだが、健康な状態であれば特に恐れる必要はないそうだが、彼らが薬剤耐性を身につけたなら、いったいどうなるのか?
耐性を持った黄色ぶどう球菌はMRSAと名をかえ、高熱や下痢を引き起こし、体内の臓器をおかし、多臓器不全から死にも至る事もある悪魔の病原菌に生まれ変わるのだ。
人類は、どこまでこの、果てしない戦いをしていくのか。
このままでは、地球上の人間以外が全部敵になり牙をむいてくるように思えてならない。
人間の繁栄の陰にひしめく犠牲になったものたちの怨念とも思える警鐘を、私たちはどのように受け止めたらよいのだろう。
物を言わず自己主張し出した自然界の人間以外の存在達、たとえるならば、モノノケにへんげした、それらと戦う力は私たちにあるのだろうか。
かく言う私は、これを書きながら、煙草の煙にむせ、激しく咳き込み、直らないのを風邪のせいにしながら、人類のいく末を少々心配する今宵であった。

夏の夜の恐い話"しょにょ3"
「おいっ !!」
おやじ32号、起電盤に潜む「なにか」に呼ばれる。(98/07/14-15:13)
私は前記に供述したように電気工事に20年近く従事しているのだが、主に建物が立った後の改修工事がほとんどだ。
電気工事と言う商売は、平日会社が操業している時はあまり忙しくないのだが、週末の土、日ともなると集中して仕事が重なり、忙しい時は10人位の職人を集め、仕事を展開する事も珍しくないのである。
その日も私は4、5人の職人を引き連れ、高台にそびえたつ研究棟で電気工事を展開していた。
その研究棟は7階建てで、はじからはじまで優に200メーターはある。
長年その研究棟に出入りさせてもらっている強みもあり、4階にある高圧電気室、それに併設されている機械室に緊急対応用に電気材料を置く事を許され、仕事があるたびにその材料資材置き場から各階の作業現場に供給する事を繰り返していた。
確か、4月の日曜日だったと記憶するが、その日はやたら蒸し暑く、じっとしていても汗が滴り落ちるほどだった。現場で材料が足りなくなり、私はやむを得ず電気室に材料を取りに行った。
その電気室は30坪ほど、小さな一戸建ての家ならすっぽりと収まってしまう広さである。出入り口は後ろと前に一つづつしかなく防音製の重い鉄の両びらきの扉だった。
重い鉄の扉を開き、奥の材料置き場に足を進めた私の後ろで、扉が自動ドアチェック(ばね式のくの字に折れ曲がる自動開閉装置)により重い音を鈍く響かせ、閉まるのが聞こえた。
私は職人が材料が足りないで仕事待ちになってしまうのが非常に嫌いだったので、すばやく材料棚に手を伸ばし、足りない材料を物色していると、私の後ろで、何かが叫んだような声が聞こえた。
ふっと気が付き電気室を見回したが、静かによどんだ空気はかすかな電気トランスの、低いうなり音以外聞こえてこなかった。
しばらくその棚を物色していたら、今度ははっきりと聞こえた。
「 おいっ!!」
私の後ろにあるのは1トン近くある高電圧のトランス達だけだったが、なぜか、その高電圧のトランスの上の方から声がしたような気がした。
それに、電気室に他の人間が入ってくれば重い扉のきしむ音ですぐに分かるはずだ。
私は「おいっ」と言うはっきり聞こえた声に一瞬おののき、電気室をくまなく見てまわった。
高電圧トランス群を収容してある鉄の大きな扉のまわりを2、3度見てまわったが、別に不信な点は発見できず、自分には耳の錯覚だと言い聞かせながら2、3歩あるくと高圧起電盤の前に出た。
起電盤とは文字どおり6600Vで入力した高電圧を各高電圧トランスに配電する主装置のようなもので建物の心臓部と言ったところだ。
その起電盤の前にも材料の棚があり、その棚を物色し、目的の材料を見つけた私は、足早に起電盤の前を通り過ぎようとした時だった。
「おいっ!!お、ま、え」
その声は空気を微妙に震わせ、直接私の鼓膜に響くようなはっきりした低い、声だった。
それに、声のした方向が、私を戦慄させた。
なんと、高圧起電盤の中からだった。その盤の中の構造はプロの立場の私は当然熟知しているのだが、人なんて入れるはずもなく、中には6600Vの帯電した電線と開閉器が設置されており、仮に人がいれば間違いなく感電し、停電はこの研究所だけでなく、この付近一帯にも波及する事故につながりかねなかった。
私は全身に汗が吹き出し、その場で動けなくなってしまった。
5分、、いや10分だっただろうか。
恐怖した私は、自分が背にしている高圧起電盤に振り返る事も出来ず、その場で固まっていると、背中に吹き出た汗が急にひんやりと感じた。
思い余って振り返る事を決心したその時、今度は私の耳元でささやくような低い頭の芯が震えるような声が聞こえた。
「お、ま、え、だ、よっ!!」
耐えていた細い糸がぷっつりと切れたように恐怖と戦慄が全身を包み込み、はじかれたパチンコ玉のように電気室を飛び出した。
全身に汗を吹き出させ、作業現場に戻った私は、職人達の前にへたり込んでしまった。
心配した職人の一人が私に向かって事情を聞きながら介抱してくれたが、とても、真実を口にする事が、出来ず、暑さのせいにしてその場をしのいだ私だった。
しばらく涼しいところで休んでいたが、そこはプロの悲しいところ、先ほどの電気室での出来事がどうしても納得がいかなくなり、引き返す事にした。
つまり、恐怖心より、技術探求心みたいなものが、自分の中で膨れ上がり、どうしても高圧起電盤を開けて見たくなったのだ。
自分の中の愚かさを唇の端でかみしめながら、研究所に常勤している電気管理者を伴ない、電気室に再び乗り込んだ。電気管理者には、高圧盤の中で異常音がしたと、その場しのぎの言い訳をすると、同行を拒まなかった。
電気室に踏み込むと、長年仕事をくれているこの研究所を、おぞましい悪霊に不法占拠される、いきどおりがふつふつと、怒りとともに吹き出しエクソシスト顔負けの勢いで私は起電盤の前に立った。
事情を知らない管理者は躊躇することなく起電盤を開けたそのとたん、何かが私の首筋あたりを通り抜けたような感じがしたが、そのあとは何も変化がなかった。
管理者は顔見知りの私を軽くののしったが、あとでコーヒーを一杯おごったら何事もなかったように、機嫌よく職場に戻っていった。
しかし、扉を開けた瞬間感じたものはいったい何だったのだろうか。
それに、不思議とその時、私には恐怖心とかの物はなく、かえって暖かい安堵感とも言うべき物が私を包み、遠い昔に分かれた親友に再会した喜びのような温かさが、込み上げ何か心がキュンと締め付けられたような気がした。
さみしい何かが、ぬくもりを求めて吹きだまり、私を招いたのかもしれない。
しかし、あの時私が起電盤の鍵を持っていたら、そして、後ろに振り返っていたら、今の私は現在、存在すらしていなかったかもしれない。
言い知れぬ不安をいだき、ときおり、この不景気にもめげそうになりながらも、今日も仕事に精を出す私だった。
次を読む