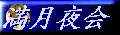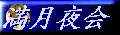
「しみ」
おやじ32号、現場に浮き出る黒いしみと格闘す。(98/07/15-20:12)
そのうちの一件の話なんだが、構造が鉄筋コンクリート(俗称 RC)で建物の規模さえ6階建ての小さな個人ビルだったが、施主が結構うるさく意外と手間の掛かった物件だったのに加え、角地にあり、脇に6m道路が走り抜け、これが隣町に走る幹線道路と直結している最悪な条件だった。
物件の正面の道路は16号線と言う大きな幹線道路だった為、昼間でも10トンの大型ダンプが、その6m道路を迂回路として通行していた。
RCを建てるにあたり、まず始めに、基礎と言う物を作らなければならない。
平均地面の高さよりも5、6m地中を掘ってコンクリートの基礎を作るのが始まりなんだが、この時から電気屋と言う商売は、現場に入らなくてはいけない。基礎のコンクリートを突き抜け、配管をし、電気を供給する必要があるからだ。
設計事務所から、電気をビルに引込む為のメイン分電盤がビルに向かって右端、つまり、角地の建物の右脇を通り抜ける6m道路のすぐ脇にあたる位置に設置する事を指示され、我々は、職人達を引き連れ直径6cmもある硬質ビニールの配管を何十本も埋め込む工事に行った。
工事も無事に終わり、次の日に大型ダンプが砕石を埋めにくるのだが、この時にも当然、立ち会っていなければせっかく埋めた配管が損傷する恐れがある。
私は、ダンプが来る当日朝の8時には現場で待機していた。
メイン分電盤の所に集まる配管は10本以上あり、束になっていたため、それが
一番の心配事ではあった角地で現場の入り口なので、ダンプがふんずけるかもしれないのだ。
私は6m道路に立ってその配管をチェックし、配管をふらつかないように支持をしていると、建築の監督がすぐに走りよってきた。
彼は、表情をこわばらせ、私の足元を指差した始めは砂ほこりで、分からなかったが、足で少し地面をこすると赤黒いシミが浮き出てきた。
「昨日事故があったんだってよ、ここで」
少し放れて見ると、80cm位のまあるい大きな赤黒いシミが道路に付いていた。私は過去に大型乗合バスに人が轢かれる瞬間を直視する苦い経験があったが、その時はそんなに驚きはしなかった。
それから一ヶ月位たった頃、建物も順調に輪郭をあらわし始めた頃、現場監督が私に向かって小声で
「また、脇の6m道路で人身事故があったんだ」と話した。
「またかよ、メイン配電盤の前?」
「そうだよ」
私は暗い気分になりながらも現場を見に行った。
何か強い力で引きずられたあとが道路にくっきりと残っており、配電盤の付くはずの配管が束ねられたあたりで、傷は途切れていた、、そして赤黒いシミが、、、。
休憩時間になり、近くのコンビニにジュースを買いに行った時、私は思い余って40代半ばの店員のおばさんに聞いてみた。
おばさんはそっけなく答えた。
「ああ、あそこの曲がり角ね、、去年は二人死んだんだよ」
「きょ、、去年、、は」
私は聞いた事に後悔していた。予想はしていたが「去年は」と来た。
これから現場の竣工から引き渡しにかけて、メイン分電盤の所での色々な作業を控えて、めまいすら起こしそうだった。
現場に戻り、職人達に複数の仕事を指示したが、メイン配電盤の仕事は、誰一人として名乗りを上げるものがいなかったのは言うまでもなかった。
それから竣工までの約一ヶ月、私は、事故現場のシミの上にベニヤ板をひき、自分に色々言い訳をしながら仕事を何とかやりとげた。
もちろん作業するさいには、線香だけは、欠かさなかった。
幸いに竣工まで、事故はなかった。
引き渡し前日になった日、一人で行くのにおじけずいた私は監督を引き連れ、例のベニヤをはがしてみた。相変わらず赤黒いシミが目に入ったが、私の脇で、監督が「洗ってみるか」と、言い出した。
二人でデッキブラシで洗ったら、意外に汚れは、簡単に落ちた。
にっこりと顔を見合わせた私と監督は、その日はそれで帰った。
次の日の朝引き渡し式のため私は朝早くに、現場に行った。
私の顔を見るなり監督が青い顔をしてメイン配電盤の方を指差しているではないか。
私はいやな予感がしたが、行って見ると、やはり赤黒いシミが浮かんでいた。
半分やけになり、近くの建材屋で黒いラッカースプレーを購入し、そのシミに缶の中身がなくなるまで徹底的に吹き付けた。
おかげで道路の一部分だけがやけに黒くテカり人目を引いたが、誰一人それを口に出すものはいなかった。
あれから何年も経ったが、思えば一番やな思いをしているのが、そのビルの持ち主だろう。
私は、今でも近くを通ると思い出すが、決してあの場所には近づかない。
「三度目の正直」
2度ある事は、3度目は?(98/07/15-23:59)当時その会社は、川崎の高津区という所にあり、結構地元のあたりでは有名な会社だった。上には県でも有名な大きな電気工事会社があり、そこの工事を下請け業者として請け負う事もしばしばあった。
高津区にO病院という個人病院なのだが相当大きな病院での事だった。
一般的に大きな施設の電気工事は入札という機構があり、県の役所に名前を連ねたそれぞれの大きな会社が金額を提示して一番安い所が請け負うのだ。
O病院の工事は何の因果か、私たちの上の会社が請け負う事となり、当然その仕事は私のいる会社に回ってきた。
さっそく社長と私は現場調査のため病院を訪れた。
O病院の事は事前に知らされていたが、行ってみて改めて驚いた。
入り口は意外に小さいのだが奥に行くにしたがってやたら大きいのだ。救急指定病院だという事も、その病院の中を見てうなずけた。
工事計画というのは、その病院の後ろに大きな空き地があり、そこに付属病棟を立て、なおかつその付属病棟の屋上に、現在足りない電気量をまかなうため、高圧受変電設備を増設しようという計画だった。
しかし、工事前に大きな問題が生じた。
建築計画のある敷地内に東京電力の高圧電線を支持するコンクリート柱が立っており、その電柱をどかさないと付属病棟の新築工事ができないのだ。
さっそく私は工事計画を東京電力と協議した結果、その際の工事にはその電柱から引き込んでいる近隣の住宅の停電が伴い、当然O病院もそれに含まれた。
大きな救急指定病院という事もあり集中治療室や緊急手術室も設備してあったので、当然停電時にはそれらの部屋に仮にでも電気を供給しないと人命にかかわる事故につながりかねない。そこで、工事当日までに敷地の後ろに仮の変電所を設け、停電時間中にそこから仮に病院内に電気を供給する事となった。
停電前日、私は親会社の工事部長といっしょに病院を訪れ停電時間の打ち合わせを済ませた。そして当日の午後の1時に停電が決まり、当日の午前中に東京電力の外線班(よく電柱にのぼって工事をしている人たち)が仮変電所に高電圧を供給してくれる手はずになった。
当日、朝の7時半に外線班を待っていると、4台ぐらいの工事車両を引き連れ作業車が現場に乗り込んできた。
さっそく班長らしき人物と挨拶を交わすと、なんかどっかで見覚えのある顔だった。よくよく話すと、何と工業高校の電気課の同級生だった。
工事も順調に進み、同級生の班長と昔話に花を咲かせていたその時だった。
作業員が登った電柱の上のほうで「ドカーーーン」という電気特有の感電した音だった。
私と班長は電柱のねっこで右往左往しているうちに、感電した本人が自力で電柱から降りてきたので一時はほっとしたが、その作業員の右手は見事にミディアムに焼けこげ、薄煙を立て、あたりに独特の芳ばしいニオイを振りまき始めた。現場はいろめき立ち、大騒ぎになりながら工事現場である救急指定病院のO病院に担ぎ込んだ。病院が近くにあるとありがたい。
「おい!!心配すんな、今仮設電気送ってやるからな」
怪我をした作業員に班長の、冗談とも思える言葉にみおくられながら作業員は、緊急処置室に消えていった。
ドタバタの間にも、さすがのプロ達は、高電圧の仮変電所への送電が時間どおりにすすめられた。そしてまもなく病院の停電時間が迫ってきた。
やっと私の出番だ。今日の朝に病院関係者との時計合わせも済ませてある。
不吉な予感を振り払い私と元請けの工事部長は、無線機片手に切り替えの為に配置についた、工事部長は古い病院側の開閉器に取り付き、私は仮設変電所の前に立った。時計を見ると、停電15分前だった。
悪夢はその時起こった。
工事部長が何かのはずみで、開閉器を切ってしまったのだ。
この開閉器というやつがくせもので、赤い小さなボタンをちょっと押せば、病院の全電力が遮断できるのだ。
後で本人を厳しく追求したが、何をどうしたのか本人もよく分からなかったらしく気がついたらそのボタンを押してしまっていたそうだ。
「魔がさした」と、しか表現できない出来事だった。
私は緊急事態を感じ取り、すぐさま仮設電気を送り込んだがどうにもならなかった。つまり、集中治療室で使用されている生命維持装置は、元の古い設備から電気を供給されているため看護婦の手によるコンセントの差し替えが必要だったのだ。
5分も経っただろうか、、
血相を変えた病院長が手術着を着たまま裏口から飛び出してきた。
「ばか野郎っ!!この人殺し!!」
病院長の一言が私の顔から血の気を吹き飛ばした。
無線機で叫んでも工事部長からの返事はなかった。
私は脱兎のごとくその場を走り出し、集中治療室へ急いだ。
私が駆け込んだと同時に集中治療室の扉が開いた。
中から病院長と数人の看護婦が出てきた。
「だっ、大丈夫でしたか?」
私は思わず叫んでしまった。
私を無視するように歩き去ろうとしていた病院長の足がピタリと止まった。
無言で振り返った病院長は、そーっと集中治療室の扉を小さく開け指をさした。
覗くとそこには人工保育器の中に手のひらに乗るような赤ちゃんがいた。
「あの子の心臓が一瞬止まりかけたんだぞ」
私は、その場で立ち尽くし、病院長に向き直り何かを話そうとしたが、言葉にならず、ただただ、とめどなく涙があふれ出てきた。
プロとしてのプライドはみじんに吹き飛び、尊い命を危険にさらした恐怖感と人殺しにならなかった安堵感、そして何より自分の目の前で息づいている生命の尊さ、、色々な思いが瞬時に頭の中を埋め尽くし、しばらく私はその場で声をかみ殺し、涙した。
後日談だが、幸いにして重傷患者達は、その時はその未熟児の赤ちゃんだけだった。
しばらくして、がっくり肩を落とした私を病院の裏口で出迎えたのは、悪魔な工事部長と、手がミディアムの作業員を連れた同級生の班長だった。
かすんだ目をこすりながら私は腕時計を見つめた。時間は2時近かった。
その日は高電圧の電力幹線の切り替えを3時から控えていたが、集まった3人、いや、ミディアム君も含めて4人だったが、全員顔を見合わせた。
重苦しい空気を破るように同級生の班長が言った。
「次は誰かが死ぬぞ」
全員の気持ちはいっしょだった。
その日はその後の予定をすべて延期し、早々に現場を引き上げたのは言うまでもなかった。
今でもその同級生は私の所に遊びにくるが、その時の話になると「日が悪かったのさ」と、さらりと言ってのける。
「開かずの間」
おやじ32号、嫁さんと幽霊旅館に泊まる。(98/08/11-01:12)
当時、当然景気はよく、旅行業界もやんやのにぎわいだった。
あれは年の暮れの12月に入って、突然正月旅行を思い立ち、彼女(今の嫁さん)を誘い宿を捜したが、当然12月に入ってからなど、有名な旅館などには空きがなく、思案した結果、さびれたとこでも我慢を余儀なくされたがとにかく宿がない、旅行を断念する事はいいだしっぺの筆者はとてもじゃないが、引っ込みが付かなかった。
本屋に走り何がなんでも宿を見つける決心で旅行雑誌を大量に買い込み、一人部屋にこもりやっきになって探した。
旅行の日取りは正月の三賀日だった。
探したかいあって、やっと2、3件めぼしい宿を見つけ、次の日早速電話してみると一件以外全部満室だった。
その空いていると言う一件の旅館は、お題目には、伊豆の全貌を見渡せる展望露天岩風呂そして、伊豆の海産物が売りだった。
その時は住所的にも駅からタクシーで15分と立地条件も申し分ない宿だったのでちょっと不思議に思ったが、わらをもつかむ思いだったので当然即決で決定した。
正月の元日から二泊三日の予約を入れた私たちは当時持っていたスポーツタイプの自家用車で、元日の昼に出かける事にした。
正月と言う事もあり気持ちいいほど、高速は空いていた。
午後の3時過ぎに伊豆の町に着いた私たちは、地図を便りに宿を捜したがなかなか見つからなかった。
伊豆の町は干物のニオイを漂わせ活気に満ちていた。
一軒の干物屋の前で車を止め旅館の場所を聞くと、先ほどまで活気のよかった干物屋の婆さんは、私が口にした旅館の名前を聞き表情を曇らせたが、親切に教えてくれた。
「ああ、あの幽霊病院の上の旅館だね」
脇にいた彼女が私の腕を強く握り締めたのは今でも記憶に残っている。
干物屋の婆さんが教えてくれた道を車で走っていくと町外れに出た。
伊豆の町と言っても盛り場は港の周辺だけで、郊外に出ると畑と野っぱらばっかりが延々と続いていた。次第に道は上り坂になりくねくねと曲がり始めた。
しばらく行くと坂の途中に白い建物が姿をあらわしてきた。
よく見ると個人病院の看板が潮風にさらされ、サビがあちこちに浮いていたが、これが婆さんが言っていた幽霊病院だなと思い、物好きの私は道路の脇に車を止め一人で降り、ちょっと建物を見る事にした。
見るからに建物は荒れ果て、とても中に入る勇気が出なかったので、その場で立ち止まり建物を見つめた。
さすがに婆さんの言った通りの幽霊病院であった。
霊感のほとんどない筆者でさえむせ返る熱気の中、背中に悪寒が込み上げ早々にその場を切り上げた。
彼女の心配をよそに坂道を進むと、山の頂上付近に目的の旅館を見つけた。
もう午後4時近かったと記憶する。
創業昭和ヒトケタを売りにしているだけあって建物は全室50あまりの大きさなのだから、想像が付くと思うが、とにかくいたるところ古い湿気を含み重くのしかかられるような不気味な感覚があふれていたのを覚えている。
駐車場に車を回しロビーに行き、名前を申し出たが、受付の従業員は何か活気がなかった。
ナカイさんに案内されるまま「はなれ」に通された。
大きなホテルの建物から少し階段を登った所にぽつりと「はなれ」は建っていた。
「お客さん東京からこられたんですか? お疲れさまでした。でも他にホテル空いてなかったんですか?」
「えっ?」
どう考えてもナカイさんの一言が気にかかったが、売りの露天風呂の事を聞いてみた。
ここには斜めに上がる小さなロープウエイがあり、それに乗って山の頂上の露天風呂に行くそうだ。
一通り説明を終わったナカイさんは、早々とお茶を出すとその場を後ずさるように部屋を出ていこうとした時、何かを言い忘れたのか部屋に戻ってくると、大きな部屋の中のひとつのふすまの前に立ち
「ここは開けないで下さいね」
と一言付け加えると困惑している私たちを尻目に、さっさと出ていってしまった。
幽霊病院、陰湿な旅館、そして開かずの間、、、三拍子そろった怪しいシュチエーションにめげそうになったが、新婚気分の私たちはそんな事も忘れ、熱い抱擁をした。
時計を見るともう6時近かった。
程なく部屋の外で人の話し声がし一瞬ビビッたが、ナカイさんが料理を運んできたらしく食器の音が聞こえた。素早くナカイさんは大量の料理を並べると帰りがけ、
「食器は明朝かたずけますんで、そのままにしておいてください」
と言い残し、まるでその場を早く引き上げたいかのようにさっさと帰ってしまった。
「普通その日に食器はかたずけんじゃないのか?」と言おうと思ったがすでにナカイさんは姿を消していた。
おまけに15畳はありそうな大きな部屋の隅に布団までひいてある始末だった。
ちょっとかんにさわった私はこのまま帰ろうかとも思ったが、目の前の多くの海の幸の豪華料理を手をつけずに帰るなんてとても出来なかった。
それに仮に帰るとしても、坂の途中には例の病院がある事を思い出しあきらめた。
はっきりいってそんな事より目の前の料理は、二人の不安をとっくにかき消していた。
たらふく海の幸を堪能した私たちは、さっそく露天風呂に行って見る事にした。
元日の夜9時ごろなのに、ひっそりと人の気配のない乗り場の二人乗りの台車は、薄明かりの裸電球に照らし出され不気味だったが、夜風が酔った二人に心地よかった。
急な山の中を古いロープウエイは、苦しそうな歯車の音をきしませ頂上に着いた。
大きな岩風呂には先客が二人ばかりいたが、混浴だったので先客は私たちに気が付き早々に立ち去った。
10畳ほどもある大きな岩風呂からは、伊豆の夜景が星空のように実にきれいだった。
が、その時。背後に刺すような視線を感じた私はビクンと体を震わせた。私の横にいた嫁さんに思わずその事を話すと、嫁さんも同じ視線をビンビン感じると言った。
腰が落ち着かなくなった私たちは早々にその岩風呂を引き上げた。
帰る途中のロープーウエイでも視線は絶えず背中をくすぐり続けていた。
とにかく自分のまわり中から視線を感じるのだ。
はっきりと人の気配がする訳でもないのに、視線だけははっきりと感じ取れた。
だいたい、山の中を通りぬけている切り立った斜面で、物好きが覗きもないだろう。
足早に部屋に帰った私たちが部屋に飛び込んだと同時に、感じていた視線が嘘のように掻き消えたのを覚えている。
しかし何か空気が重く湿っている。
振り返ると、開かずの扉が目に入った。
何か鈍いモーターのうなりのような波動を感じた私たちは、部屋の隅の布団に飛び込んだ。
抱き合っていると不思議と恐怖感は薄らいだ。
私たちは残ったビールを飲み干しさっさと寝てしまった。
不思議と熟睡できたらしく明朝ナカイさんの声に起こされた。
予定ではもう一泊するとこだったが、遠慮したのは言うまでもないだろう。
結局、死ぬほど恐い目には合わなかったが、あの無数の視線は尋常な事ではなかった。
あまり深く考えると恐怖がよみがえってくるので、この辺でこの話は止めておこう。