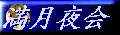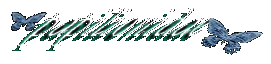
「南米にメネラウスを追って行った時の事です。
深い樹林の中で、迂闊にも道を見失ってしまい、先生と私は丸一週間、樹林の中を彷徨いました。 ですがその日も次の日も全く状況は変わらず、辺りはどこまで行っても深い森が続くばかりで、何か質の悪いトラップにでもかかったかのような錯覚さえ覚え始めた頃、食料も水も残りわずかとなって、さすがの僕らも焦り始めたのです。 焦りは、簡単に不安に、そして恐怖へと変わっていったのです。
あなたも収集家のお一人なら、あの地方の気候をご存じでしょう? 青年は一頻り話すと、紅茶をひと口すすった。
窓の外では、風が一層激しく吹き荒れていた。 「人間だれしも自分の死が目の前にぶら下っていれば恐ろしいと思うのが当然ですが、さすがの先生もその時ばかりは、恐ろしいと思われたのでしょうね。夜ともなれば、辺りは漆黒の闇に包まれ、僕らはわずかな焚火だけを頼りに身を寄せ合って眠ったのです。 ………その時、僕には先生が、先生には僕が、………僕だけが、唯一生命ある同胞だったのです」
その瞬間私は、それまで淡々と話していた青年の顔が艶然と輝いたような気がした。
「隣に寝ている先生の息があるかどうか確かめるのが、僕の毎朝の日課でした。こんなに広い世界の中で僕たちは全く孤立していたのです。先生と僕と。本当の二人きりでした。 青年はソファーから立ち上がり、壁一面に掛けられた蝶を背にじっと私を見つめた。 「多分、………僕たちは、そういった状況の中で、次第に少しづつ、狂っていったのかも知れません」 青年の目は、遥か彼方の熱い森を見つめていた。
|