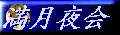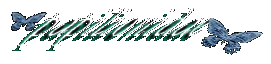
「あれはそうなってから何日目の事だったんだろう。 僕にとっては、そんな事はもうどうでも良かった。僕は、そういった状況にある事がむしろ嬉しかった。なぜなら、先生にとって、この僕が蝶より何より重要な存在となり得ていたのですから。何よりその事こそが喜びとなっていたのです。 すでに僕の心の中には、先生と二人きりで、この暑い森の中を蝶を追いながら永遠に彷徨い続けるという甘美な幻想が住み着いていたのです。寸断される眠りの中で、暗く、暑い森の奥に消えていく僕らの姿を、何度夢に見たか知れません。 助けだされる前日の明け方、まだ、陽も十分に上がりきっていない時間でした。
気がつくと、シュラフの中に先生がいらっしゃらなかった。
………おかしいですよね。 ・・・・・・でも、先生は、その場所からさほど離れていない茂みの中に、茫然として座り込んでいらっしゃったのです」 青年の薄い胸が、ゆったりとしたシャツの中で、暖炉の炎に照らされ薄赤く浮かび上がった。
「僕は、素直に身体の赴くまま、自分の墓を捜していた方が良かったのかもしれない。 その時の先生は、確かにまともな状態ではいらっしゃらなかった。 茂みの中に背を向けて座っていらっしゃった先生を見つけて、僕は小走りに駆け寄りました。そして、その背中に触れようとした瞬間、先生は、まるでそれを知ってでもいたかのようにゆっくりと振り返って、僕をじっと見つめられたのです。
その時の先生の瞳の奥の妖しい輝きを僕は今でもはっきりと覚えています。 青年は、ゆっくりと息をついだ。 「あれは、目標としている蝶と出会った時、それを今まさに捕まえようとなさっている時の先生の目でした。
あの暑さの中で、僕はこの身が凍り付いていくのを感じました。 『君、蝶を見ただろう?』 ……やっと聞き取れるほどのお声で」 青年は、壁に掛かった標本箱の端を指先でつつとなぞりながら、さも面白い事を話しているかのように低く笑った。 「『そうです、先生。僕と一緒にメネラウスを捜しているのですよ』
……こういう日に話すと、何だか悪いジョークのようですよね。 『メネラウスなんてどうでもいい! 君は、今、……見なかったのかね? 今ここで、今し方だ・・・・・人の姿をしていた。翅は・・・・・・翅はパルナシウスだった。そこの薮にいて、私をじっと見つめていたのだよ!』 ………その弱り切っている身体の、一体どこからそんな力が出ているのか、先生は僕の肩をぎしと捕まれたまま、すごい剣幕で怒鳴られたのです」 青年の話は次第に熱を帯びていった。私は、まるで私自身もその場にいたかのような、湿気た熱い空気を肌に感じていた。 空気は澄んで冷たいのに、そこここに留まる昼間の暑さにもやぐ明け方、熱帯雨林で、おそらくはその状況が見せた幻覚だったのだろうが、彼は、本当にそれを目撃したに違いないのだ。パルナシウスの翅を持つ、人の姿を。 「先生は、その晩高い熱にうなされ、正直もう長くはないだろうと思われました。僕の父ほどお年を召しておられる方です。無理がたたって当たり前、僕はといえば、ただおろおろと側にいるだけで、何をして差し上げることもできなかった。 そうしているうち悪夢のような一夜が明け、次の日の昼頃、奇跡的に近くを通り掛かった英国人のパーティーに救われたのです。
|