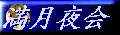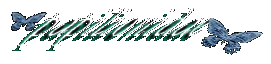
その旅行を境に、先生は変わってしまわれました。 確かにもともと蝶に対しては異常なほどの執着を持った方でしたが、それからというものは、まるで仇のように蝶を乱獲されるようになったのです。この屋敷の標本の大半は、その日以降先生が採集されたものなのです。 僕は、始めの内こそ、先生のお供をして各地を回っていましたが、あまりに無茶な獲り方をなさるので、たった一度だけ抗議をしたのです。 それきりです。 それ以来、先生はいつもお一人で出掛けられるようになりました。先生のいない何ヵ月もの間、僕は、ここでただ先生を待つだけの暮らしが続くようになったのです。
先生は今どこでどうしていらっしゃるのだろうか、また蝶の虜になって苦しんでいらっしゃるのではないだろうか……。先生が無事に戻られる事だけを祈る日々が続きました。 青年の、グレーに近い薄いブルーの瞳が壁に掛かったたくさんの蝶の斑紋の中から、私をじっと見つめていた。線の細い顔に暖炉の炎が映って一層くっきりと際立たせていた。 蝶は、斑紋によって敵を欺くというが、私の目の前にいるこの人の形をしたものは、一体本当に息をしているのだろうか。
この屋敷に来れば、彼が十年前にそうしたように、喜びと親しみを込めた微笑で出迎えてくれるはずだった。ここで私を待っていたのは、死んだ彼の魂だったのかもしれない。 暖炉の中で、一際大きくばちりと薪の爆ぜる音がした。 「しばらくの間は、相変わらず色々な蝶を追いかけていらっしゃいました。それが、一頭十頭と集めていくうちに、今まであれほど輝いていたコレクションが、色褪せて見えるのだとおっしゃるようになったのです。 すでにあのパルナシウスの幻影に取り憑かれていらっしゃったのかも知れません。
先生のご旅行のお供をしている間は、僕を決してお側から離されず、本当にわずかな時間でも離れれば、必ずどこかから先生の視線を感じていました。 ………僕が、あのパルナシウスではなかったのかと」 彼の魂が、私の中で大きくどきんと脈打った。
|