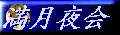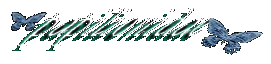
その時不意に窓ガラスの一つが大きく音をたてて開いた。 暖炉の中で、それまで静かだった炎が狂ったように燃え盛った。 部屋の温りが一瞬にして奪われ、表の凍てついた空気が激しい勢いで吹き込んだ。
青年が、吹き込んでくる風に逆らって窓に近づいていった。 「君、その傷は………」
壁に掛かっていた標本箱の一つが床に落ちて、大きな音をたてて砕けた。 「これですか?」
足元で、砕けた標本箱のガラスが、ざりりと鳴った。
両の肩口から首の付け根を通り背中に二本、腰の辺りまで、大きく裂かれたような傷跡だった。つけられてから、まだ日も経っていないようなものと思われた。
「あの暑い森の中で狂ってしまったのは、先生だけではなかった。
先生から疑われるほど、お心がこの僕に向かえば向かうほど、僕は、それこそどんなに長い間でも先生を待つ事ができました。
先生は、僕を捕らえた蝶のように扱いました。傷つけぬよう、折らぬよう、それでいて蜘蛛が獲物を捕らえた時のように決して逃がさぬように。 そうして待ち続けていくうち、僕は、本当にあのパルナシウスは、僕自身であったのだと、錯覚するようになっていったのです。 ………もっと疑うがいい、責めるがいいと……… このパルナシウスの身体が、先生を思うように翻弄しているのだという事に、快感をさえ感じていたのです」 青年は、その傷をいとおしむかのように、ゆっくりとシャツを戻した。
|