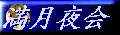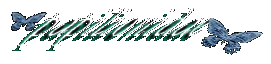
「先生が、半年程のご旅行から戻られた時でした。半年、といえば、先生がこのお屋敷を離れるにしては、長すぎる時間でした。 先生の事はもちろん心配でしたが、大学側の要請もあって、五ヵ月が経つ頃から二、三日、四、五日と日にちを区切って大学に戻り、先生の残されたものの整理などにかかっていました。運悪く僕がこの屋敷から離れていた時、突然先生がお戻りになったのです。
僕は直ぐ様呼び戻され、このお屋敷の一室に閉じ込められたまま、いつもより一層激しい尋問を受けました。いつもの甘やかな喜びなど嘘のようでした。 その時の先生は、もう僕の知っている先生ではありませんでした。
幾日も、幾日も、疲れ果て意識の無くなるまで責め苦は続きました。 そうして何日か過ぎたある日、先生は手に鋭い刃物を持って僕を閉じ込めていた部屋へとやってきたのです。 殺される、と思いました。今日、僕は、先生に殺されるのだ、と。でも、不思議に恐ろしくはなかった。その瞬間までがあまりに長かった為なのか、疲れ果てていた為なのか、おそらく、あの甘やかな時間の果てにそれがあるであろう事は、無意識ではあってもずっと以前から覚悟していたのかも知れません。 まるで、刑場に引き出される前のイエスにユダがそうしたように、先生は私に以前と変わらぬ、その手に持ったどきどきと鋭い刃とは全く裏腹なキスをしてくださいました。 ああ、と思ったその瞬間、肩口に鋭い痛みが走り、シーツが血で染まりました。 翅を出せ、と。正体を現すのだ、と。低い声で呟きながら、先生は僕の身体を切り裂いていきました。
………僕は、遠退いていく意識の中で、ああ、これで僕にも翅が生えるに違いないと、はっきりと思いました。
青年の足元で微かに、蝶の屍の砕ける音がした。
|