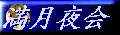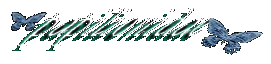
「僕は、それでも死ななかった。先生の思う姿にもなれなかった。
先生は、その日から徐々に衰弱していかれました。 青年は、足元で砕けるガラスを無視したまま、ゆっくりと暖炉に近づくと、炎の中に薪を足した。 「僕のこの身体からパルナシウスの翅が生えてきさえしたなら、先生はずっと側にいてくださったに違いない。僕があのパルナシウスではないと気づく事さえ無かったら、僕はそのままそれまで通り先生のお帰りをずっと待っていられたし、どんな仕打ちを受ける事も厭わなかった………その事を考えると、今でも眠れない夜があります」 青年は、ゆっくりとソファーに腰を降ろし私を見つめた。
「しかし、君………君が、彼に殺されていたかもしれない」
僕の生命の尽きるまで、先生のお側に行ける日まで、僕はこのままここで、その日を待ち続けるつもりです。 部屋の中には、燃える炎の匂いのする暖かさが戻っていた。
「大学に戻る気は無いのかね。彼の残したものを受け継いでいく気は無いのか」 「先生は、………」
何もかも諦めた人間というものを、私は臨終の床にある父を見舞った時に初めて見た事がある。父はその全てを知っていて、自分の死の時間さえ見事に予言してみせたのだ。 「先生は、ここにいらっしゃいますから………。 もう、僕は、先生がどこかで苦しんでおられるのではないかと心配する必要も無くなりました。先生を待ち続けたあの長い時間に比べれば、今、こうして先生のお側にいられる事が、どんなにか幸せと思えるのです。それに………」 青年は、一つ呼吸をおいて続けた。 「先生の残してくださったこの傷跡から、パルナシウスの羽が出てくるのではないかと、今も思うのです」
|